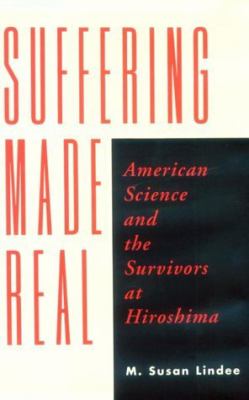Lindee, Susan. Suffering Made Real: American Science and the Survivors at Hiroshima. Chicago University Press, 1997.
広島と長崎への原爆投下後、放射線の遺伝影響研究はABCC(原子爆弾傷害調査委員会)の中心課題となった。スーザン・リンディーはアメリカの原爆調査の歴史を検討した著書 Suffering Made Real: American Science and the Survivors at Hiroshima 第4章でABCC の遺伝研究に焦点をあてている。
リンディーはABCCの遺伝影響研究を当時の遺伝学をめぐる状況とあわせて説明する。ABCCは当初、被爆者自身に対する放射線の生物的影響を調べることを計画していたが、それはすぐに彼らの子孫への放射線の遺伝影響調査を中心とするものへと変化した。その背景には、アメリカ合衆国原子力規制委員会などの遺伝影響は被爆者自身への影響よりもより恐ろしいものであるという認識に加え、一般社会の高い関心があった。ABCCの遺伝プロジェクトは内部のマネジメントと一般へのインパクトの双方で中心課題となったのである。
遺伝プロジェクトはとりわけ「誤解」されやすいものであった。1940年代までの遺伝研究には、遺伝学の手法の問題と優生学との関わりという、科学的及び社会的な難しさが取り巻いていた。そのため、被爆者に遺伝影響が起こることは確実であると思われていたが、ABCCの遺伝影響研究は有意な影響を示せずに失敗すると思われていた。ところが遺伝学のおかれた社会的状況は1950〜60年代を通して変化していく。リディーは、マラーやニールといった遺伝学者たちが広島と長崎で行った遺伝影響研究が、人間の遺伝形質へのより科学的なアプローチを示すものとして、生物学におけるビッグサイエンスの先駆例となったと指摘する。そのシステムを支えていたのは、日本人スタッフや妊婦、その他の研究材料たちであった。
(本書の邦訳は出版されてない。)
– Maika Nakao
![[Teach311 + COVID-19] Collective](https://blogs.ntu.edu.sg/teach311/files/2020/04/Banner.jpg)